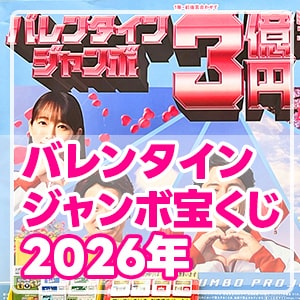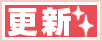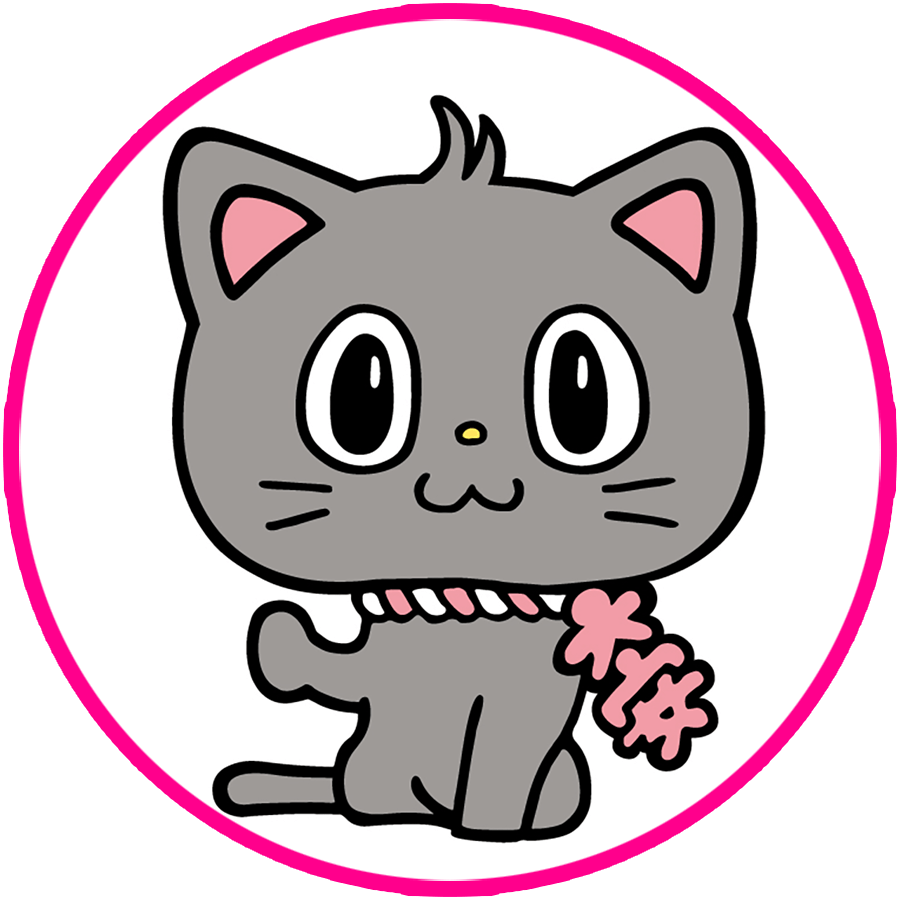大安吉日カレンダードットコム
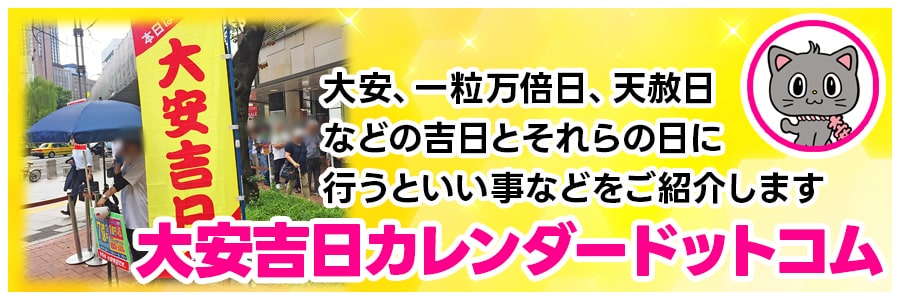
大安、一粒万倍日、天赦日などの吉日とそれらの吉日に行うといい事などをご紹介
こちらのページも人気のページです
更新
2023年の干支 癸卯(みずのとう)はどんな年?

毎年年始になると「今年の干支は〇〇なので、こういう年になる」といったようなことが言われます。
この「〇〇」の部分で使われるのが、十干十二支です。
2023年はその十干十二支の「癸卯(みずのとう)」の年。癸卯の年がどんな年なのかを見て、2023年がどのような年になるのかを見ていきましょう。

2023年は癸卯の年。その癸卯はどんな意味で、その年はどんな年になるのか?見ていこうにゃー (≡^ω^≡)
「十干十二支」とは?

十干十二支とは正しい意味での干支であり、「干」と「支」の組み合わせで「えと」です。
※日本人が日常使っている干支(えと)は、正しくは十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)であり、「じゅうにし」です。
十干十二支とは、十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支が組み合わさることで、60通りの組み合わせがあり、年・月・日・方位・事柄などを表すのに使われます。
甲子(きのえね)からはじまり、癸亥(みずのとい)で終わる組み合わせで、この
60の組み合わせで物事が一巡するという考え
が生活の様々や慣習で取り入れられています。
その代表的なのが還暦で、この考えを元に生まれてから60年で生年の干支を迎え、一つの人生を生ききったということを意味しています。
2023年の癸卯は十干十二支の40番目の年
先述の十干十二支の60の組み合わせは、それぞれの年にも振られており、2023年の十干十二支である癸卯は
十干の10番目にあたる「癸(みずのと)」
と
十二支の4番目にあたる「卯(う)」
が重なる、
十干十二支で40番目にあたる「癸卯(みずのとう)」
の年となります。
癸(みずのと)とは?

十干の「癸(みずのと)」は、十干の10番目最後にあたるものであり、生命や物事の終わり意味するとともに、「揆(はかる)」につながる文字で、植物の内部にできた種子が測れるほど大きくなり、春の間近にして萌え出ずる用意をしている様を意味しています。
卯(う)とは?

また「卯」は干支ではうさぎのことですが、十二支の語源としては「茂(ボウ、しげるの意)」または「冒(ボウ、おおうの意)」で、草木が茂り地面を蔽うようにになった状態を表しており、春の訪れを感じるという意味。
また「卯」の字自体は左右に開かれた門であり、冬の門が開き飛び出る様子の意味もあるとか。
卯は草木が土を割って芽吹き、やがて地面を覆い繁茂の勢いを示しています。
卯=うさぎ自体が勢いよく飛び跳ねる生き物であり、多産で成長も早いため繁栄の象徴でもあります。
なので卯年は勢いよく飛び出る年、飛躍する年もと言われます。
2023年 癸卯はどんな年になるの?

この「癸」と「卯」の二つが合わさる2023年の干支癸卯の年は
2023年「癸卯」の年は
これからの成長や飛躍のために力をため準備し育んできたことが十分に実り、芽吹き始める年。
早い人は大きく飛躍し、一気に広まり始める、努力がいっぺんに実り始める年。
と言えるでしょう。
これまで努力してきたことや、実直にしてきたことが報われる、花開き一気に飛躍する年になりそうですね。
また努力やためてきたことが足りない人でも、年のはじめから努力を重ねれば年内には花開き、結果につながることも考えられる年でもありますね。

2023年癸卯の年はこんな年になるのにゃ。こういった謂れを参考にして、2023年もいい年にしていこうにゃにゃー (≡^ω^≡)